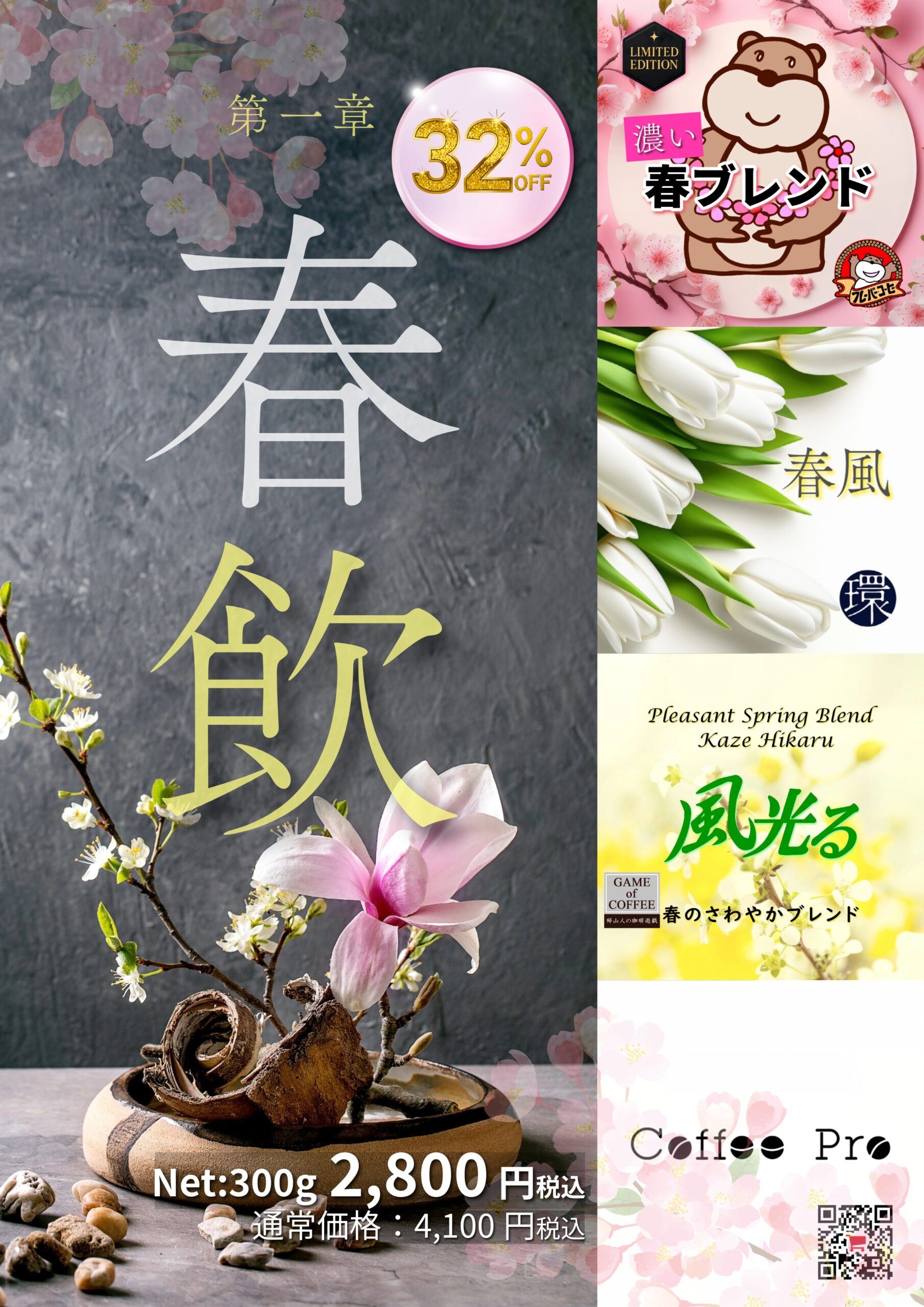2000年ごろにホームページでプレゼント募集をやっていました。
そこでは色々いな質問をしていろいろな面白い回答があったのです。
あなたのお気に入りのインターネット通販ショップを教えてください。 まだ通販をしたことのない人はあなたのお気に入りのサイトを教えてください。
(こんな人が書いてくれました)
楽天市場 楽天市場、豊富なので好きです。(女 32歳)
ムラウチ 八王子にあるムラウチという電気屋さん?? の通販サイトです。 品揃えもナカナカだし、使いやすいと思います。(男 42歳)
キッチンウエアカフェ 『キッチンウエアカフェでは、台所用品を中心にインターネット専用で格安にて販売しています』 (女 35歳)
e・veryD 『エブリデイ・エクスプレスは、スーパーマーケットの商品をお宅までお届けいたします。』 (男 52歳)
摩周ジンギスカンのざき ここでは何度かお肉を買っています。 安くておいしいの典型のようなお店です。 これからの行楽シーズン、バーベキューにも うってつけですよん。 (女 36歳)
ENGEINET 花の種の種類の多さに感激! (女 36歳)
ヨドバシカメラ (男 25歳)
梅の月向農園 手作りの梅で作ったとてもおいしい梅干しを販売しているとこです。オーナーの方がどんな畑で作っているのか、写真がのっているし、メールを書けばすぐに返事をくれます。とても、親切だし、とにかくおいしい!! (女 25歳)
HANABISHI 花菱という洋服のオーダーメイドのサイト。わたしはここのシャツがお気に入りです。これまでに6着作りました。(女 29歳)
升田養蜂場 『ミツバチと共に生活する広島県の養蜂家です 』(女 32歳)
アオハラ 文化の源、アオハラ(男 39歳)
中国茶王国「彩香」コーヒーは一番大好きな飲み物だけど、次に好きな飲み物が中国茶なので、ここは時々覗き、購入します。(女 33歳)
Shop@AOL(女 23歳)
bellne千趣会のネット通販です。日用品まで揃うので重宝しています。(女 33歳)
JTBおみやげNET『全国から選りすぐりのおみやげが大集合』(女 35歳)
GLAMOUR『グラマー』では、がんばってプレゼントに応募してますが・・・当たってません。 こちらは、今回初めて読ませて頂きました。 感動しちゃいました。 いつも何気なく飲んでるコーヒー・・・やっぱし奥は、深かった。 これだけ、コーヒーを『愛』してらっしゃる方からすると、私は邪道なんだろうか・・・。 とっても勉強になりました。 早速、コーヒーを入れてみますね♪ あ、後、空き缶の『お湯さし』作ってみます! ありがとうございました。 (女 36歳)
VIRTUAL YAOYA バーチャル八百屋さん とてもいいものを提供してくれてます (女 28歳)
最終更新日:2016年 9月 28日 (水)


![ElInjertoSet 【DFR環】特別企画「インヘルト SET」[中深煎り]200g](https://coffee-pro.jp/wp-content/uploads/2026/01/ElInjertoSet-409x409.jpeg)