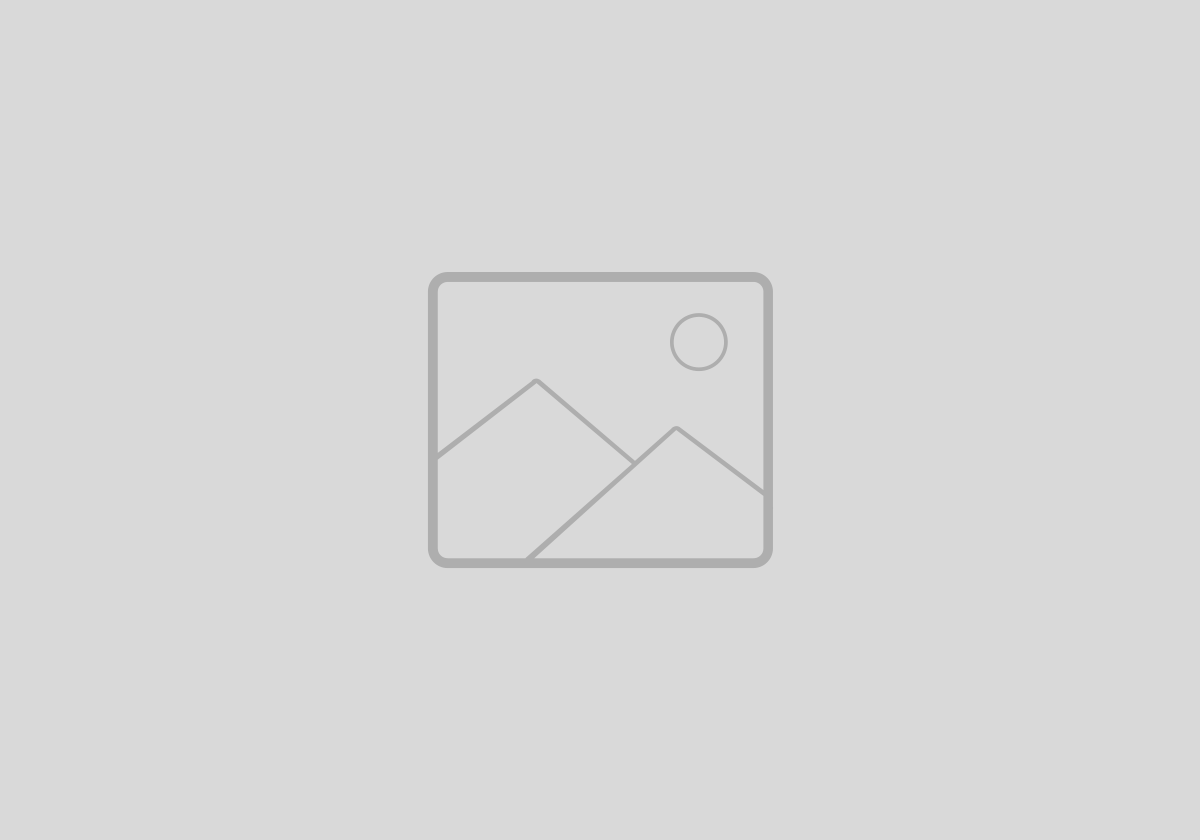7月12日(水)
今日もいろいろと忙しいのです。
ちょっと、遠くまで配達があったりあったり、夜にはちょっとした会議に 出席しなければならなかったりと大変な一日でした。
もしも今日、自由な時間があったら、バーナーの高さ調節器とバーナー目詰まり解消装置の ふたつともつくる事ができたのにひじょーーーに残念でした。
(ちゃっかりと、バーナー目詰まり解消装置の方は、つくっちゃいましたが・・・・)
たぶん、明日は完全にそのふたつの装置を完成させるつもりなのです。
このふたつの装置は、構想三ヶ月、製作はたったの2日なんです。(めちゃめちゃ簡単そうーー)
実は、どんな装置であっても、うちの場合次の日には焙煎機を動かさなければならないので 一日で改造するようにしているのです。
(そのための準備は、もっともっと時間をかけますが・・・)
この仕事を10年ほどやっていますが、今回の改造ほどわくわくする改造は ありませんでした。
だから、まちがいなくうまくいくと思います。
この焙煎機で焙煎したコーヒーは、今までのうちのコーヒーとは明らかに違いがでるはずです。
それに成功したら、一気に三段跳びをやったぐらいにぼくとしては進歩するような気がします。 (わくわく)
7月13日(木)
焙煎機の改造に毎日熱中しています。
(じつは、この2日ほどですが・・・)
今日は、6時ぐらいから改造を始めたんです。
とんとん拍子に改造が進み8時ぐらいには改造が終わってしまいました。
大体改造というのは、夜中までというのが今までのパターンだったので あまりの速さに僕自身がびっくりしてしまいました。
こまごまとしたチェックを済ませて焙煎機に火をいれても 何も問題なく動きます。
「こんなはずではない。こんなにはやく終わるはずがない。」てなことを おもいながら、細かいところをチェックしていたら、ありました。
みごとなミスがありました。完全にやり直しです。
結局、夜中まで改造は続きました。めでたし。めでたし。
7月14日(金)
今日は、焙煎機の改造が終わって試運転の日です。
今回の改造は、今までいろいろと改造をしてきましたが、その中でも 最高に成功した改造だと思います。
コーヒーの味が大きく変わるのです。
すごくモカは、モカらしい味になるのです。
(今までの焙煎はなんだったんだろう・・・・・)
何度目かの焙煎をしているとき、バルブとバーナーをつないでいる継ぎ手(ユニオン) の部分から火が吹き出しました。いわゆる、ガス漏れです。(この程度ではあわてない)
他の店の改造の場合ガス漏れなどがないか継ぎ手の部分に洗剤などをぬって調べるんですが 今回は、めんどくさいのでやめちゃったんです。
いくら慣れていても初心に返って確実なチェックをしなければいけないなぁと思いました。
(そういいながら、たぶんやらないと思う)
また、今回の改造もそのうちホームページに載せますのでみてやってください。
とりあえず、今日はいい日でした。
(ガス爆発もなかったし・・・・)
7月15日(土)
名古屋の「S」くんが、打ち合わせにきました。
知り合いの「O」さんがホームページをつくるんで「S」くんに お手伝いを頼んだんです。
(なぜ、待ち合わせがうちの店なんだろう・・・・)
2人の打ち合わせが午後だったんですが、
そのときにうちの店の奥にいたのが男ばっかり、8人
午前中にうちの店の奥にいたのが女の子ばっかり5人
もうちょっと、まざってきてほしいなぁ。
なんといったって、男ばっかりだと店が明るくないし、 むさくるしいんです。
(集まっていたみんなが、同意見)
つくづく女性は、華だと思いました。
(だいたい本音、ちょっとおべんちゃら)
7月16日(日)
日曜日は、ぼくひとりなのでのんびりホームページをつくることに
決めているんです。
しかし、今日はなぜかアイスコーヒーが足りなくなってしまって 焙煎をするはめになってしまいました。
(本当は、いいことなんですがねぇ・・・・)
ぼくひとりなのに焙煎はやらなきゃいけないわ、 接客はしなくっちやいけないわでてんやわんやでした。
一生懸命働いて、 アイスコーヒーの在庫がある程度できたので、 いつもどおりホームページをつくろうと思ったら あまりにも真面目にハンドピックなどをしたので 疲れて眠くなってしまいました。
というわけで、ホームページの更新はぜーーーんぜんできませんでした。
7月17日(月)
今日は、知多半島の方でコーヒー屋をやっている「Y」さんが あそびにきました。
(「Y」さんとは、メールなどで親しい)
最初は、うちの店の焙煎機の改造の話をしていました。
そのうち、「Y」さんの焙煎機の改造の話になっていきました。
またまたそのうちに、どのように改造すればいいかというような 具体的な話になってきました。
ぼくは、機械の改造の話になるとわくわくするんです。
そして、今まで眠たくても一気に頭がまわりだすんです。
実際に、改造後の焙煎機が明確にイメージできましたから 焙煎機の改造はできるでしょう。(キッパリ!)
このぐらい、学生時代に頭がまわっていたら苦労はしなかったろーーに!
7月18日(火)
今週の日記は、ほとんど焙煎機の改造で 埋め尽くされています。
実際読み返しても、大きな改造だったなぁと しみじみ思います。
その分日記も手抜きをしたなぁと、まじまじと思います。
(今週の日記は、ほとんど赤色を使っていない)
その代わりといってはなんですが、
コーヒーに関しては非常に進化したと思います。
コーヒーに関する進化がホームページにも
そのうち反映するでしょうから気長に 期待していてください。